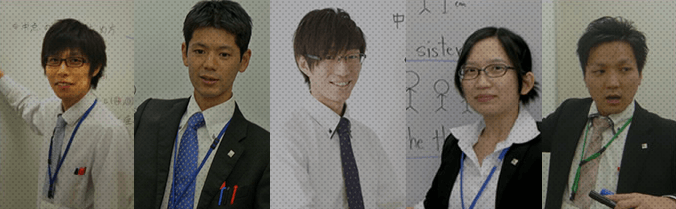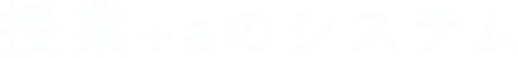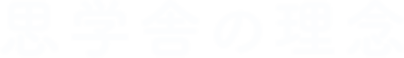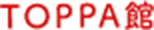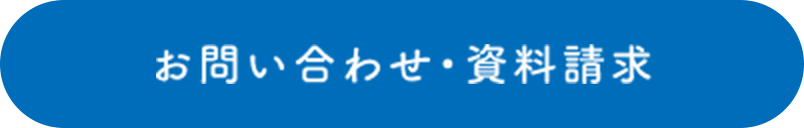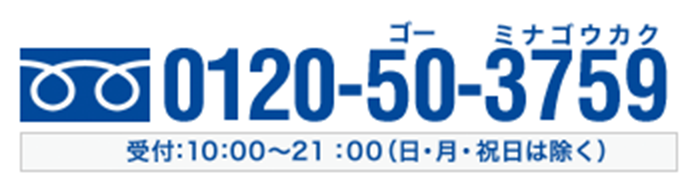イベント情報・お知らせ記事
「具体」を「抽象化」して「本質」を見抜こう【学習コラム】
こんにちは!思学舎 土一・竹園TOPPA館土浦校です!
※今回のブログは少し長くなりますが、国語の読解練習だと思ってゆっくり読んでみてください。(笑)そして、少しでも参考になりそうな部分があれば、是非日々の学習に取り入れてほしいと思います。
今回は、「問題演習をやっているのになかなか点数があがらない」という方へ、オススメの学習法をご紹介します。
それはズバリ、「具体」を「抽象化」し「本質を見抜く」ことです。
・・・これだけだと、ピンと来ませんよね。詳しく説明していきます。
初めに、出題される問題というのは、必ず作問者の意図があって作られています。
例えば、
中2理科の間違えやすい内容で「胆汁は肝臓で作られ、胆のうで蓄えられる」というものがあります。これに対して、
「胆汁を作るのは胆のうである。〇か×か」
という問題があるとしましょう。これは、作問者がこの問題という「具体」を使って「胆汁が作られるのが、『胆のうかどうか』」という知識=「本質」を確かめようとしています。
ただし、作問者は確かめたいレベル・焦点(視点)に応じてこの「具体」を変えます。
先ほどの
「胆汁を作るのは胆のうである。〇か×か」
これは、「胆のう」 か 「否」か のみを確認しようとしていますが、
「胆汁を作るのはどこか」
という問いにすれば、「肝臓」を確認しようとしている
「胆汁を作るのはどこで、蓄えるのはどこか」
→作るのが「肝臓」で蓄えるのが「胆のう」であることを同時に確認しようとしている
「肝臓で作られ、胆のうで蓄えられる液は何か」
→先ほどとは逆に「胆汁」を確認しようとしている
というように問題=「具体」のバリエーションは変わります。ただ、どの問題であっても、「胆汁は肝臓で作られ、胆のうで蓄えられる」という受験で覚えるべき「本質」を確認するための「具体」であることに変わりないですね。
このように、作問者は能力や知識といった「本質」的なものを測るために、問題という「具体」を使い確かめるのですが、皆さんが問題に間違えたときに、この「本質」を理解しよう・押さえようという気持ちがなければ、次も間違えてしまい、「本質」の成長には繋がりにくいのです。
問題演習はしっかりやる。言われた宿題はしっかりやっているが、なかなか成績が伸びない。あるいは、別の聞かれ方をすると答えられないという人は、この問題という「具体」を「抽象化」し、この問題で問われているポイント=「本質」は何かを見抜こうとしていない可能性が高いと思います。
それこそ極端な話、「胆汁を作るのは胆のうである。〇か×か」という問題だけを繰り返し、「胆汁を作るのは胆のうじゃないんだ!」ということだけを分かって満足してしまい、「では実際どこで作られるのか。」「胆のうとは何をするところなのか」を調べようとする気持ちがなければ、先ほどの別パターンの問題=「具体」で正解することができず、いつまでたっても作問者が身に着けてほしい「本質」が身につきません。
もちろん、堅苦しく毎回全ての問題に対して「今回の『具体』を『抽象化』するとどうなるだろう・・・」と考える必要はありませんが、間違えた問題は「もう一度関連知識・解法から覚え直す」という習慣をつけるようにすることで、「本質」の養成につながりますね。「答えを模写する『作業』で終わり。」「理解の伴わない丸暗記で終わり。」では成長しないのです。
そしてこれは、勉強に限った話ではありません。
例えば、運動部では、よく走り込み・筋トレをしますね。これらのトレーニング=「具体」をするだけで、野球でホームランが打てるようになったり、サッカーでハットトリックを決められるようになったりするわけではありませんね。
それでも、野球やサッカーには持久力や筋力といった「本質」が必要不可欠だから練習をしますし、「9回裏まで全力で攻守できるようにするんだ」「試合時間90分バテずに反応できるようにするためにやるんだ」というように、「具体」を「抽象化」することで、練習効率が上がり「他にもこういったトレーニングをするべきだ」というのが見えてきそうな気がしませんか。
また、他の例を挙げてみましょう。皆さんがカレーの作り方という「具体」を学んだとします。もしかしたらもうすでに一人でカレーを作れる子がいるかもしれません。
ただ、このカレーの作り方を完璧に丸暗記したのにも関わらず、「ポトフ」や「クリームシチュー」、「ハヤシライス」の作り方が一切わからないような人になってしまったら悲しくないですか。それぞれのレシピごとに丸暗記するのは非効率ではありませんか。カレーのレシピを覚える過程で
「食材ごとにこういう大きさに切るとこういう食感になる・火が通りやすくなる」
「食材の堅さに応じて、こういう順番で何分くらい煮込むと良い」
というように、カレーのレシピという「具体」を「抽象化」して、料理をする上でのポイント「本質」を学び、他の料理にも応用できるようにしたいですよね。
長くなりましたが、このように「問題演習はしっかり真面目にやるのに、別の問題では解けない」という人は、その問題のポイント=「本質」は何かを考えるようにしてみてはいかがでしょうか。覚えるべき知識・解法は何なのか。それらはどのように活用できるのか、抜けていたらしっかり復習する。間違えた問題に対して、「この問題って要するにこれが大事だったよね」という「本質」を確認するように意識してみましょう。目の前の問題=「具体」をやっただけで満足するようにしないことが大事です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。